地球の7割を占める海に生息する魚たち水産物は豊富だが、有限でもある。その水産物が枯渇するのを防ぐため、人々は養殖をする道へと進み始めた。
海の幸に恵まれている日本でも養殖産業は注目され、効率的な養殖を実現するために多くの研究が実施されている。
今回、今まで勘に頼っていた養殖業者のサポートになると期待されているシステムを、Googleの持株会社であるAlphabetが次世代技術の開発拠点として設立した「X」が開発した。
>>X 開発者ブログ
海中にいる魚を正確に数える作業はコストがかかり過ぎた
 Photo by Hanson Lu on Unsplash
Photo by Hanson Lu on Unsplash
養殖を行う際の課題は山ほどあるが、中でも運用コストの半分以上を占めるのが魚たちを育てるための餌代だ。餌ひとつとっても、多すぎると食べかすが環境を汚染し、少なすぎると魚たちが十分に育たないという難しさがあった。ゆえに、いけすのなかにいる魚の数を正確に把握することが大切であったが、そのノウハウは養殖業者の勘頼りだった。
具体的な魚を数える方法もある。たとえば、魚を別のいけすに移す時だ。これは、ダイバーが潜っていけすへの通り道を動画撮影し、その動画を人の目で見て1匹ずつ確認する方法だ。しかし、この方法では確かに具体的な魚の数値が確認できるが、時間や人的コストがかかり過ぎた。
そこで今回、熟練者に依存している作業を機械で自動化する試みが行われた。
養殖魚の自動追尾・記録技術
Alphabetの機密機関であるX社は、新しい技術を用いて世の中の難しい課題を解決することを目標にしていて、気球を用いたどこでもインターネット回線プロジェクト「Project Loon」や、血糖値をモニタリングできるコンタクトレンズプロジェクト「Google Contact Lens」などの研究や開発をしている。
今回開発されたのは、養殖魚の自動追尾・記録システム「Tidal」だ。Tidalによって海面下で何が起きているのかを高精度でデータ化することに成功した。
Tidalは、個々の魚を検出・解析できる。その魚がちゃんと餌を食べたか、その時の水中温度や水中酸素濃度など、いけす内の総合的な環境をデータとして記録する。このデータを養殖業者が活用すれば、効率よく餌の量をコントロールしてコスト・汚染削減に繋げられる。
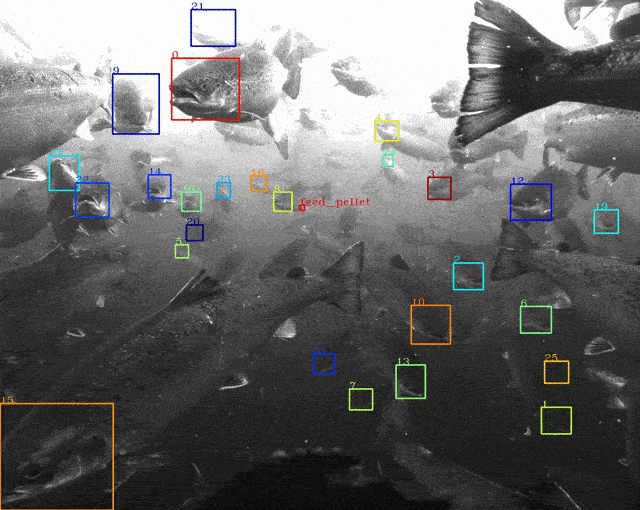 画像はXの開発者ブログから(ブログのGIF画像とはフレーム数が少し違います)
画像はXの開発者ブログから(ブログのGIF画像とはフレーム数が少し違います)
Tidalには機械認知の技術が組み込まれていて、主にコンピュータビジョンの応用形であるマシンビジョンの技術で実現している。上記GIF画像を見てみると、人の目では追いつかないスピードで魚を認識、追尾しているのが確認できる。さらに、水中を漂う餌もひとつ単位で認識し、それを食べた魚のタグを随時変化させている。人間の目ではできない仕事だ。
Xはこのプロジェクトで得た経験と情報を有効活用し、他の専門家や組織と一緒にさらなる環境問題解決を目指すという。養殖業界にとって目からうろこのような技術は、Xにとって環境保護に向けた一歩でしかないのだ。
"魚" - Google ニュース
March 12, 2020 at 07:00AM
https://ift.tt/2TX5Mof
海面下の養殖魚を自動追尾する技術、米AlphabetのXが開発 - Ledge.ai
"魚" - Google ニュース
https://ift.tt/2Xkxf4q
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update

No comments:
Post a Comment